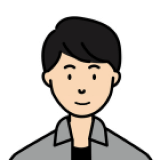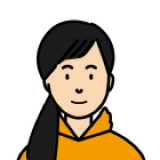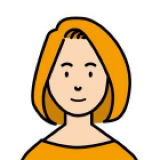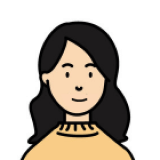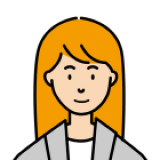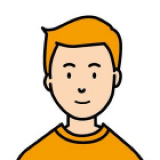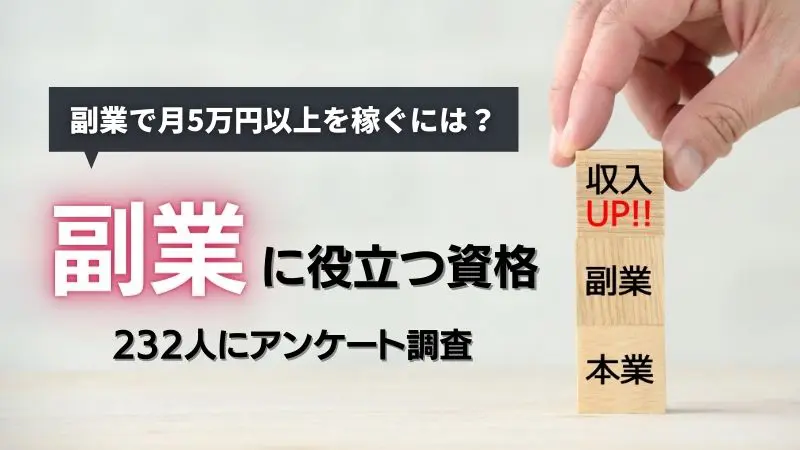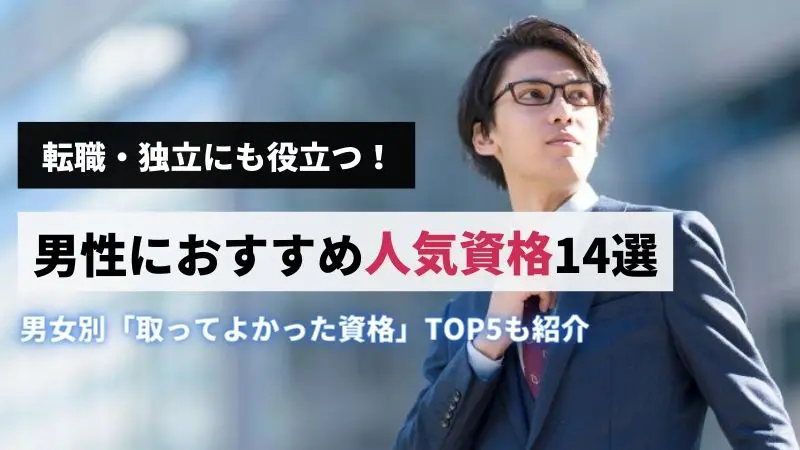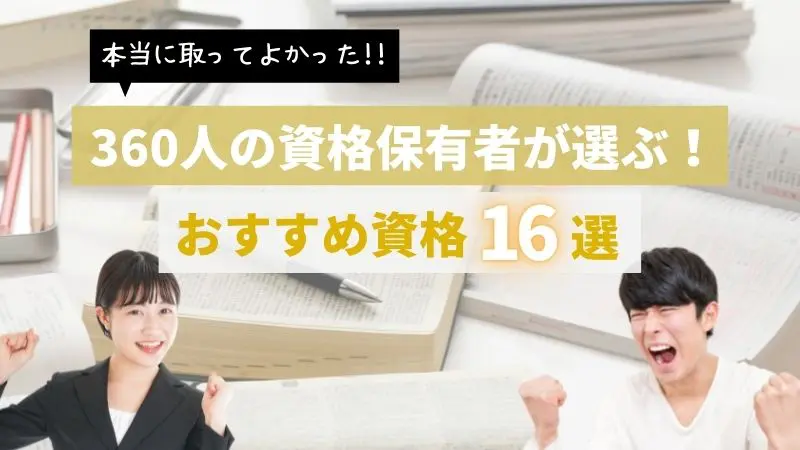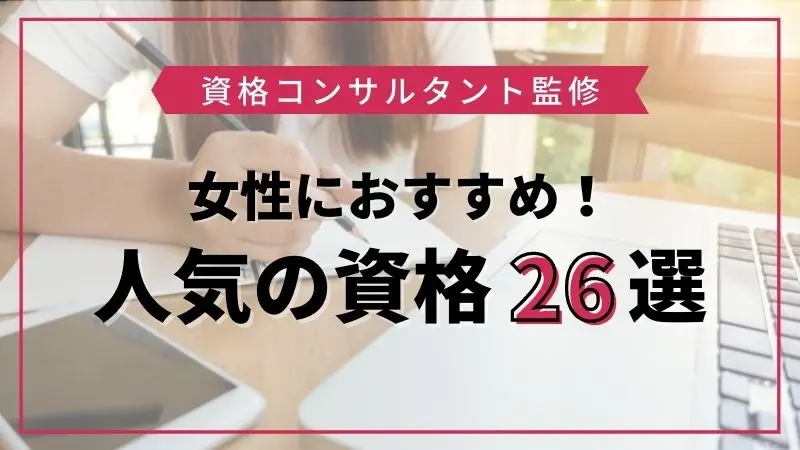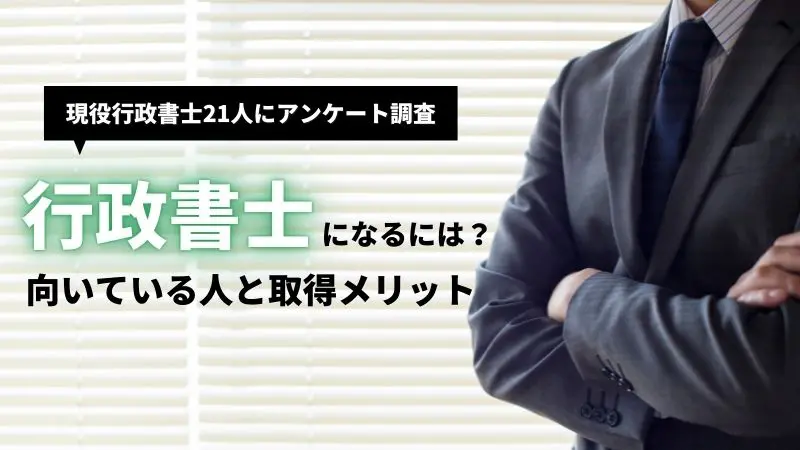
行政書士になるには?資格の取得メリットから試験概要や難易度まで解説
目次
「行政書士とはどんな資格?」
「行政書士は社労士や司法書士とどう違うの?」
法律系国家資格として有名な行政書士ですが、資格取得で行えるようになる仕事や関連資格との違いなど、詳しく知れられていないことも多いですよね。
そこで、この記事では行政書士の仕事内容や関連資格との比較、資格試験の概要などとともに、資格保有者21人のアンケート調査に基づいた資格取得のメリットについても解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
調査方法:インターネット調査
調査対象:行政書士の資格保有者21名
アンケート実施期間:2022年8月15日~2022年8月19日
※本記事エラベルが独自に制作しています。メーカー等から商品の提供や広告を受けることもありますが、コンテンツの内容やランキングの決定には一切関与していません。※本記事で紹介した商品を購入するとECサイトやメーカー等のアフィリエイト広告によって売上の一部がエラベルに還元されます。
行政書士とは

行政書士とは、行政書士法を根拠とする国家資格です。
官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成を行ったり、提出手続を代行したり、諸手続きに関する相談などに応じる専門職のことを指します。
行政書士が作成できる書類には以下のようなものがあります。
- 官公署(役所など国、地方公共団体の諸機関)に提出する許認可等の書類
- 遺産分割協議書など権利義務に関する書類
- 実地調査に基づく図面類など事実証明に関する書類
作成できる書類の詳細についてはこの後の行政書士の業務内容で詳しく解説していきます。
行政書士の業務内容は、代書的業務からコンサルティングまで幅広く、行政手続きの専門家として活躍することが期待されています。
行政書士の独占業務とは?主な業務内容
行政書士の業務内容は、大きく下記の3つに分かれます。
まずはこれらの行政書士が行う業務内容についての理解を深めておきましょう。
書類作成
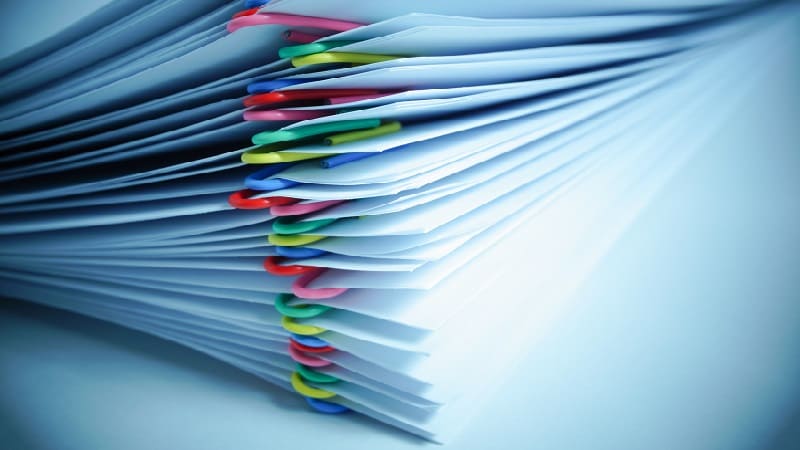
行政書士が作成する書類で主なものは、「官公署に提出する許認可書類」「権利義務に係る書類」「事実証明に係る書類」が上げられ、その数は1万種類以上とも言われます。
弁護士や司法書士、または事業当事者などが作成できるものも含まれますが、ほとんどの書類作成は行政書士の 特定の資格を有する者でなければ、携わることを禁じられている業務 とされています。
■行政書士が作成できる許認可書類例
- 建設業許可
- 飲食業許可
- 風俗営業許可
- 古物商許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可
■行政書士が作成できる権利義務に係る書類例
- 遺産分割協議書
- 各種契約書(売買、賃貸借、委任など)
- 念書
- 示談書
- 内容証明
■事実証明に係る書類例
- 実地調査に基づく図面類
- 議事録
- 会計帳簿
- 賃借対照表
- 損益計算書
以上のように、行政書士が作成する書類は多岐にわたります。
行政書士の資格を持たない人が行政書士の独占業務を行ってしまうと、行政書士法違反となり、処罰対象となるので気をつけましょう。
手続きの代理

行政書士の代理業務には書類作成のほか、作成した書類を官公署へ提出する手続きの代理までもが含まれます。
たとえば、行政書士は、以下のような手続きの申請を代理で行うことができます。
- 法人設立の申請
- 飲食店の営業許可申請
- 自賠責被害者請求等の申請
- 農地転用の許可申請
- 帰化申請
行政書士が代理人として行える範囲は書類作成とその手続きの代理までであり、依頼人の相手方と交渉することまでは弁護士法に抵触するため、行えません。
相談

行政書士は、書類作成のみならず、それに伴う相談も業務として行います。
たとえば、飲食店開業にともなう許認可申請の書類を作成しながら、依頼人の役に立つ情報を提供するなどコンサルタント的な業務も重要な行政書士業務の1つです。
行政書士の資格以外にも独占業務資格はたくさんあるのでもっと知りたい方はこちらの記事もチェックしてみてください。

将来性のあるおすすめ国家資格一覧|独学で取れる資格から注目の最新資格まで紹介
行政書士になるための要件
行政書士になるためには「行政書士の試験に合格すること」と、考えるのが一般的ですが、実は試験免除で行政書士資格を得る方法もあります。資格要件は、行政書士法第2条で定められています。
資格要件は大きく3つで、以下のいずれか1つの要件を満たす必要があります。
以上の方法で行政書士となる資格を取得した者は、行政書士会に入会し、行政書士名簿へ登録を受けることで晴れて行政書士となれます。
それぞれ詳しく解説していきます。
行政書士試験に合格する

行政書士法に基づき、毎年行われる行政書士試験に合格する方法です。行政書士となるために最もベーシックな方法と言えるでしょう。
行政書士試験の概要
行政書士試験は、行政書士法に基づき、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識および能力について行われます。
| 受験資格 | なし(年齢、学歴、国籍等に関係なし) |
|---|---|
| 日時 | 毎年1回 11月の第2日曜日 午後1時から午後4時まで |
| 申込方法 | 郵送・インターネット ※毎年7月下旬受付開始 |
| 場所 | 全国の会場 |
| 受験料 | 10,400円 |
| 公式サイト | https://gyosei-shiken.or.jp/ |
本年令和4年の試験実施日は、11月13日(日)の予定です。しかし、受験申込み受付は8月で締め切っているので、今から受験を検討している人は、今からじっくり対策を練って来年11月の受験合格を目指しましょう。
受験申込みは、毎年7月下旬から8月下旬までの1ヶ月間で、郵送の方が受付期間は若干長く設定されています。
参考:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和4年度行政書士試験のご案内」
関連する法律系資格を取得する
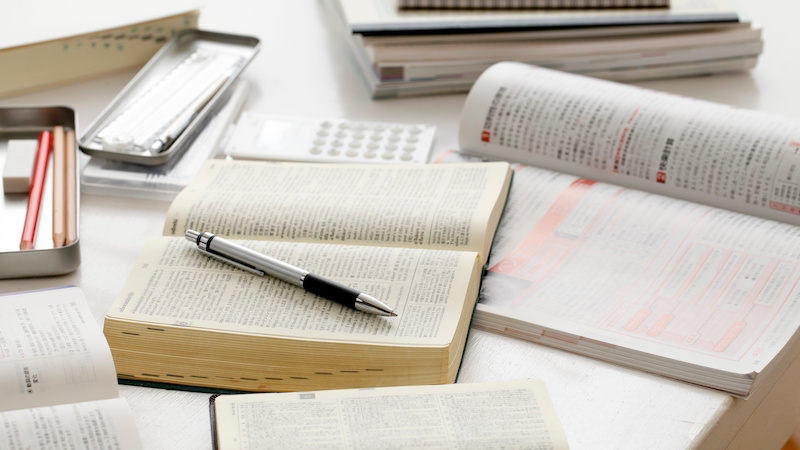
弁護士、弁理士、公認会計士となる資格を有する者は、同時に行政書士となる資格も有していることになります。
これら法律系資格を有する者は行政書士試験を受験し、合格する必要はありません。
公務員として一定の勤続年数を重ねる

国または地方の公務員として行政事務を行った期間が通算して20年以上(高等学校・大学等を卒業した者は17年以上)となる者は、行政書士試験を受けることなく、行政書士資格を有します。
行政書士試験の難易度
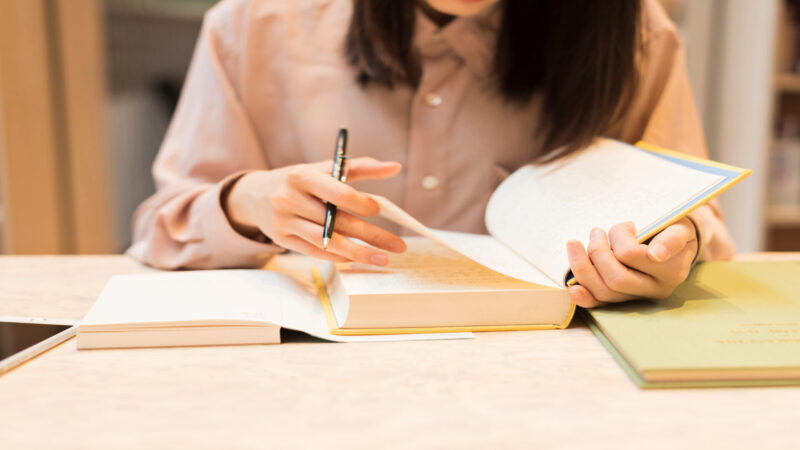
行政書士の合格率は、過去10年間では8〜15%ほどで推移しています
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 47,870人 | 5,353人 | 11.18% |
| 令和2年度 | 41,681人 | 4,470人 | 10.72% |
| 令和元年度 | 39,821人 | 4,571人 | 11.48% |
| 平成30年度 | 39,105人 | 4,968人 | 12.70% |
| 平成29年度 | 40,449人 | 6,360人 | 15.72% |
| 平成28年度 | 41,053人 | 4,084人 | 9.95% |
| 平成27年度 | 44,366人 | 5,820人 | 13.12% |
| 平成26年度 | 48,869人 | 4,043人 | 8.27% |
| 平成25年度 | 55,436人 | 5,597人 | 10.10% |
| 平成24年度 | 59,948人 | 5,508人 | 9.19% |
参考:一般財団法人行政書士試験研究センター「最近10年間における行政書士試験結果の推移」
このように合格率を見ると、行政書士試験の難易度は比較的、高いと言えることがわかります。
行政書士試験の試験科目と合格基準

行政書士の試験科目には「行政書士の業務に関し必要な法令等」と「行政書士の業務に関連する一般知識等」があります。
行政書士の業務に関し必要な法令等には、憲法、行政法、民法、商法、基礎法学が含まれ、合計46題です。
行政書士の業務に関連する一般知識等には、政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解が含まれ、14題からなります。
以下の表が、試験科目の詳細をまとめたものです。
| 試験科目 | 出題形式 | 出題数 | 満点 | |
|---|---|---|---|---|
| 法令等 | 択一式 | 5肢択一式 | 40問 | 160点 |
| 多肢選択式 | 3問 | 24点 | ||
| 記述式 | 3問 | 60点 | ||
| 計 | 46問 | 244点 | ||
| 一般知識等 | 択一式 | 5肢択一式 | 14問 | 56点 |
| 合計 | 60問 | 300点 | ||
参考:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和3年度行政書士試験合否判定基準」
合格基準は以下のようになります。
- 法令等科目の得点:122点以上
- 一般知識等科目の得点:24点以上
- 試験全体の得点:180点以上
行政書士試験の合格にはこれらをすべて満たすことが必要です。
行政書士の資格を取得するメリット

行政書士の資格を取得しても、就職・転職で大きなアピールポイントになるなど積極的に活用できなければ、勉強する甲斐がないですよね。
そこで、行政書士の資格保有者21人に行ったアンケート結果を基に、資格取得のメリットについて紹介します。
■行政書士取得のメリット
では、それぞれ資格保有者からのリアルな意見を参考にしながら解説します。
独立開業に役立つ

アンケート調査のなかで「独立開業に役立つ」と答えた人は、21人中で8人いました。そのなかから3人の回答を紹介します。
独立開業できるのは行政書士の大きなメリットです。実際に開業して成功するためには、資格だけでなくコミュニケーション能力や営業スキルも必要になりますが、資格取得が独立の足がかりになるのは間違いありません。
行政書士に向いている人については記事の後半で詳しく紹介します。
転職で有利になる

行政書士の資格が転職に有利になると答えた人は、21人中8人と、メリットとして独立開業を挙げた人とまったく同数でした。
行政書士の資格があれば、業界を問わず広く就職・転職で有利にはたらくとの回答が目立ちました。業界の垣根を超えて役立つ資格なので、キャリアアップのために取得しておくのもいいでしょう。
また、直接行政書士を活かせる仕事でなくても難関と言われている国家資格を保有しているということは「努力できる人」「目標を達成できる人」という認識をしてもらいやすく、そういった点でもプラスになります。
法律の知識が身につく

独立開業や転職以外の回答で目立ったのが、法律の知識が身につくことでした。21人中4人が言及しています。
企業経営において、経営戦略やリスク管理などの行政手続きや法律的視点は必要不可欠なので、そのうえで行政書士の資格は大きな武器になります。
また法律知識は、仕事以外にも時には私生活でも役立つ場面が多くあります。自分で開業する時や、家を建てる時など、どういった手続きが必要になるのかを把握し、自分で進められる力があると強いですよね。
行政書士の平均年収

行政書士の平均年収について、ネット記事ではおよそ400万円とも600万円とも記載されています。
難関の国家資格の割には思ったより低いな…と思った方も多いのではないでしょうか。
実際のところ、行政書士の平均年収について国が実施する統計調査は存在せず、明確な根拠はありません。日本行政書士連合会が実施する全国的な報酬額統計など関連データはありますが、こちらでも正確な年収までは把握不可能です。
行政書士は、行政書士事務所・法律事務所に務める場合や一般企業に就職する場合、また独立開業する場合など、働き方によって年収は大きく左右されることを理解しておきましょう。
行政書士の就職先とは?

行政書士の資格を取ってすぐに独立開業とイメージする人もいるかもしれませんが、自ら仕事を取る営業力がないと安定した収入を得るのは非常に困難です。
行政書士として働ける場所としては、次のような就職先があげられます。
- 行政書士事務所
- 法務事務所
- 弁護士事務所
- 企業の法務部(不動産業界・金融業界など)
まずは、行政書士としての実務経験を積んで独立するための力をつけるのもおすすめです。
現役行政書士21名に聞く「行政書士に向いている人」
行政書士にはどんな人が向いているのでしょうか。こちらも資格保有者21人に対して行ったアンケート調査を参考にして解説します。
事務処理能力が高い人

事務処理能力やコツコツと継続的に作業できる適正を挙げていた人は、21人中で半数近くいました。
行政書士の仕事で代表的なもののひとつが書類作成です。会社設立や営業許可など重要な書類を取り扱うため、高度な事務処理能力を持った人が向いているという意見には納得できます。
コミュニケーション能力が高い人

高いコミュニケーション能力を発揮できる人物が、行政書士に向いているとの回答も多かったです。
行政書士は独立開業するとなると自分で仕事をとる必要があるので、コミュニケーション能力や営業スキルは欠かせません。書類作成など事務仕事のイメージが強いかもしれませんが、積極的に人と関わっていく能力も必要となります。
人のために動ける人

依頼人の立場でものごとを考え、行動できる人が向いているという意見です。
行政書士の業務には、遺言・相続など人間として依頼人と深く関わるものもあるので、このような業務も苦にすることなく、人のために奉仕できる精神が行政書士には求められています。
行政書士の学習方法
行政書士の資格取得を目指すには、独学や通信講座、スクールの選択肢があります。
実際に資格保有者はどの学習スタイルで、どんな教材や通信講座を利用して試験に合格したのかを参考にしながら解説しました。
独学
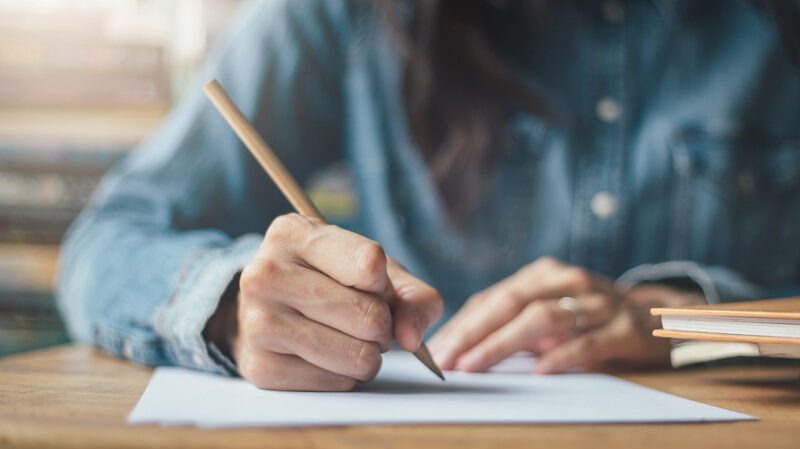
独学で学習したという人はアンケート回答者21人中10人と、ほぼ半数でした。
これらの回答以外でも、過去問を中心とした問題演習を繰り返すことが重要という意見が多かったです。独学は、自分で必要な教材を揃え、計画的に学習できる人には向いているでしょう。
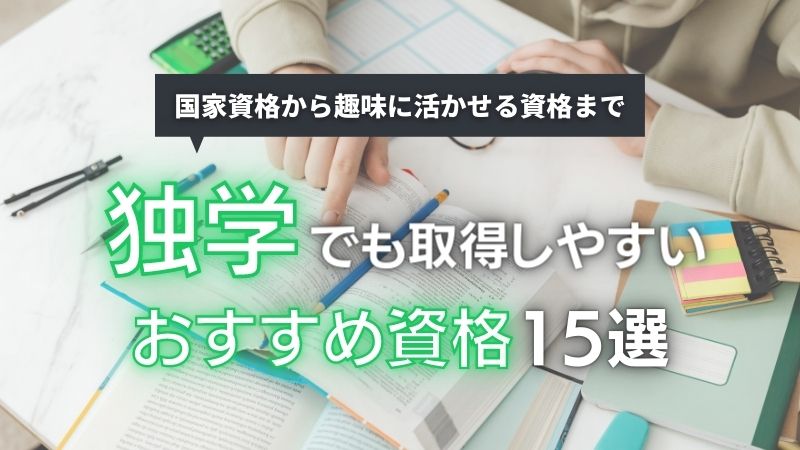
独学で取れる難易度別おすすめ資格15選|簡単に取れる国家資格から趣味に役立つ資格も
通信講座

通信講座で学習をしたと答えた人は21人中8人と、独学で学習した人と同程度の数にのぼりました。
通信講座なら自分で参考書や問題集を選ぶ手間が省け、信頼できる教材がまるごと手に入ります。また、添削・質問を受けられるので、在宅でありながら理解不足や誤解を放置せず学習を進められるのもメリットです。通信講座はスクールと比べると費用もリーズナブルなので、多くの人におすすめできる学習方法と言えます。
| 通信講座名 | 特徴 | 行政書士講座の費用 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| ユーキャン | |||
| キャリカレ | |||
| たのまな | |||
| フォーサイト | |||
| スタディング |
もっとおすすめの通信講座を知りたい方は「おすすめの通信講座7選」をチェックしてみてください。
スクール

通学スクールで学習をしたと回答した人は、2人でした。ここではスクール名がわかっている回答のみ紹介します。
スクールなら、何より講師から直接アドバイスを受けられるのがメリットです。ともに学ぶ仲間と出会えるのもスクールならではでしょう。独学が苦手で強制的に学習できる環境を手に入れたい人にはスクールが向いています。
行政書士と司法書士の違いは?

行政書士とよく間違えられやすい資格として司法書士があげられます。
司法書士は、「街の法律家」と呼ばれる法律専門の国家資格です。
行政書士も司法書士も業務として書類作成、手続きの代理を行いますが、大きな違いとしては、専門分野が異なります。
行政書士は官公署へ提出する書類の作成や手続きの代理などを行いますが、司法書士は法務局に提出する書類の作成や登記・供託手続きの代理行います。
また、どちらも難関資格ではありますが、行政書士の合格率が毎年10%前後なのに対し、司法書士の合格率は毎年4%前後とより難易度が高い資格です。
行政書士と社労士の違いは?
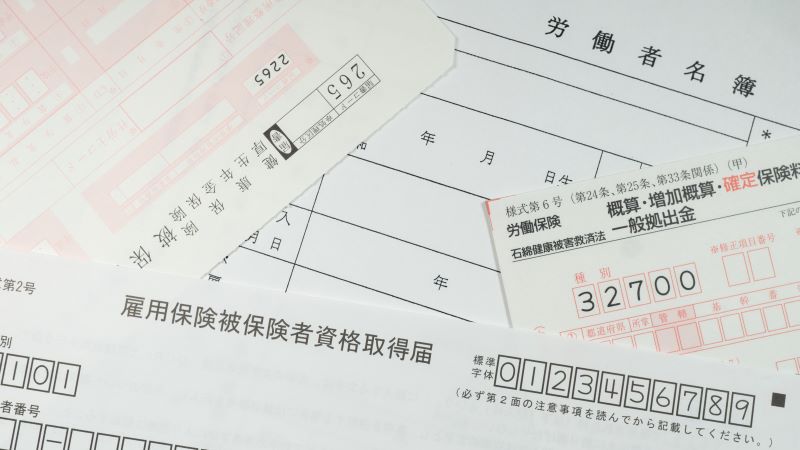
行政書士と同じ法律専門の国家資格として、社会保険労務士(社労士)もあげられます。
社会保険労務士は労働問題や社会保険制度などの専門家です。
行政書士の業務は許認可申請など行政手続きに関するものですが、社労士はより身近な労務関係や社会保険、年金などの領域が主な専門分野です。
先ほど紹介した司法書士同様に社会保険労務士の試験合格率も非常に低く、毎年6%前後であり数ある国家資格の中でも難関資格の1つです。
行政書士と関連性のある資格と難易度
前章で紹介した行政書士と同じ法律系資格として、以下の資格ものがあります。
これら国家資格について、難易度など行政書士と比較するとどのような違いがあるのかなどについて解説します。
宅地建物取引士

| 難易度 | 行政書士より易しい |
|---|---|
| 受験資格 | なし |
| 受験料 | 7,000円 |
| 試験月 | 10月 |
| 合格率 | 17.9%(令和3年度) |
宅地建物取引士は、宅地・建物の売却や購入におけるアドバイスをする不動産取引の専門家です。
不動産取引には多額の金額がともなうためトラブルを回避し、公正な取引を実現するため、宅建業法に定める重要事項の説明などができます。
宅地建物取引士の過去10年における試験の合格率はおおむね15%を超えており、過去10年間で8〜15%ほどの行政書士よりやや難易度的に易しいと言えるでしょう。
参考:一般財団法人不動産適正取引推進機構「試験実施概況(過去10年間)」
司法書士

| 難易度 | 行政書士より難しい |
|---|---|
| 受験資格 | なし |
| 受験料 | 8,000円 |
| 試験月 | 7月 |
| 合格率 | 5.1%(令和3年度) |
司法書士の業務は、登記または供託手続きの代理が主なものです。
家や土地など不動産を購入したときは登記をして公に権利を示す必要がありますが、このような登記手続きを司法書士が担います。
司法書士試験は行政書士試験と同じく誰でも受けられますが、難易度には違いがあります。司法書士試験は筆記試験に加えて口述試験も課され、試験の合格率は過去5年では4〜5%台で推移しているように行政書士より難易度が高いです。
社会保険労務士
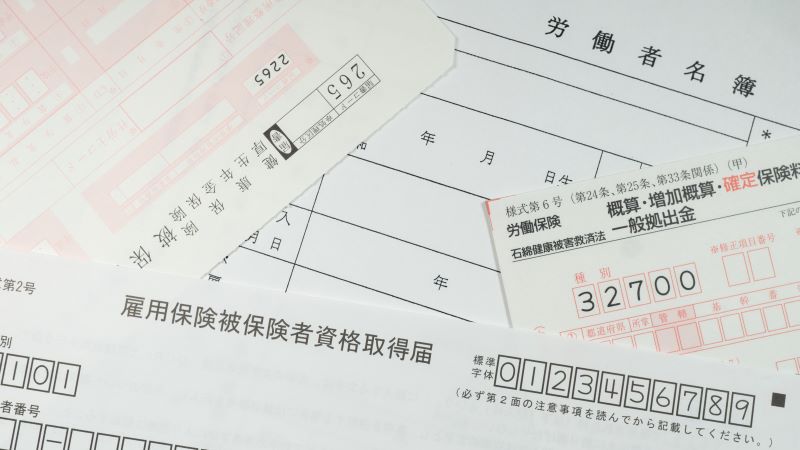
| 難易度 | 行政書士と同程度 |
|---|---|
| 受験資格 | 学歴や実務経験によって異なる |
| 受験料 | 15,000円 |
| 試験月 | 8月 |
| 合格率 | 7.9%(令和3年度) |
社会保険労務士は、労務や社会保険、年金相談など、働く人の利益に資する業務を行います。就業規則の作成・運用や毎月の給与計算・賃金制度の構築を行うほか、公的年金に関する唯一の国会資格者として業務を遂行する専門家です。
行政書士と社労士とのダブルライセンスがあれば、会社設立に関する書類作成・申請代行からその後の労務管理までワンストップで行えるメリットがあります。
また社労士試験には受験資格があり、そのひとつが行政書士試験の合格です。ダブル受験を考えている人は先に行政書士に合格しておくといいでしょう。
まとめ
行政書士の資格について紹介してきました。資格取得のメリットはこちらです。
行政書士のメリット
独立開業できるのは行政書士の大きな魅力のひとつですよね。独立せずとも、転職で有利になるという資格保有者の意見も多かったので、キャリアチェンジ・キャリアアップ目的で行政書士資格を取得するのもいいでしょう。
行政書士は資格試験は難易度が低いわけではありませんが、関連する法律系資格のなかでは取得しやすいとも言えるでしょう。未経験で学習する人も、必要に応じて通信講座などを利用しながら対策すれば、合格を狙うことは十分に可能です。

「選ぶをもっと楽しく」をコンセプトに、専門家・愛好家・体験者の方にご協力頂きながら、買い物やサービス選びに悩む方たちをサポートします。一人ひとりにフィットした情報に届け、皆さんの「したい」を叶えます。
※記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がエラベルに還元されることがあります。メーカー等の依頼による広告にはPRを表記します。
※掲載されている情報は、エラベルが独自にリサーチした時点の情報を掲載しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。