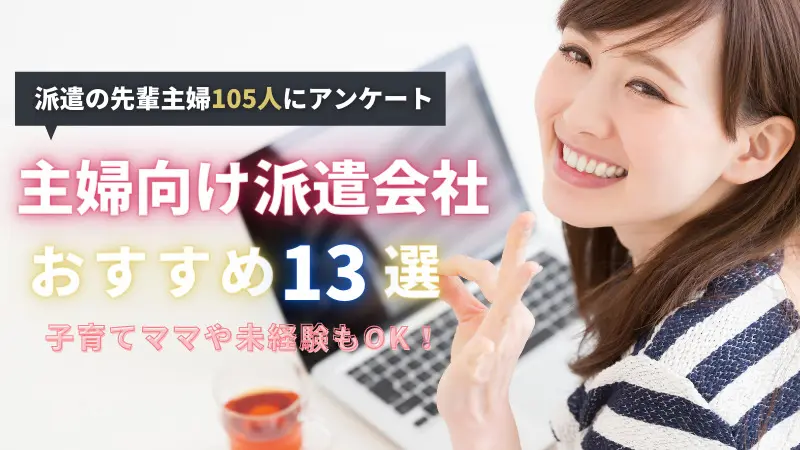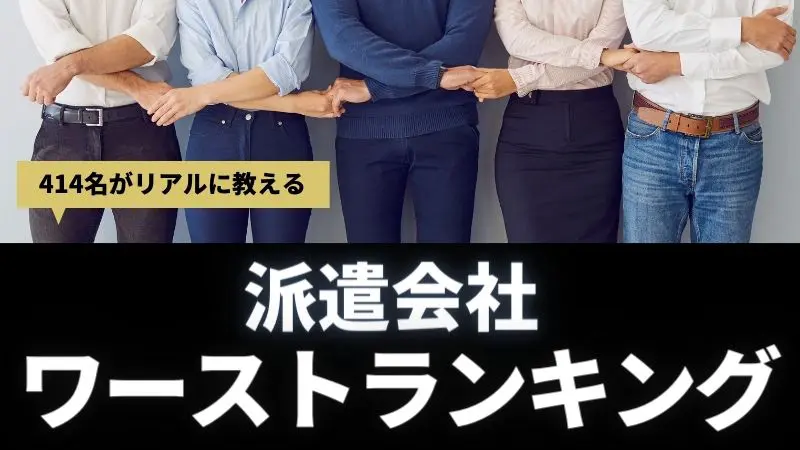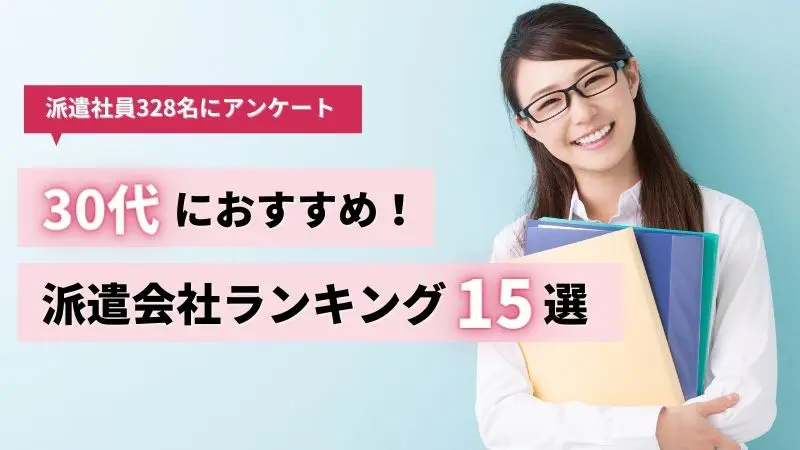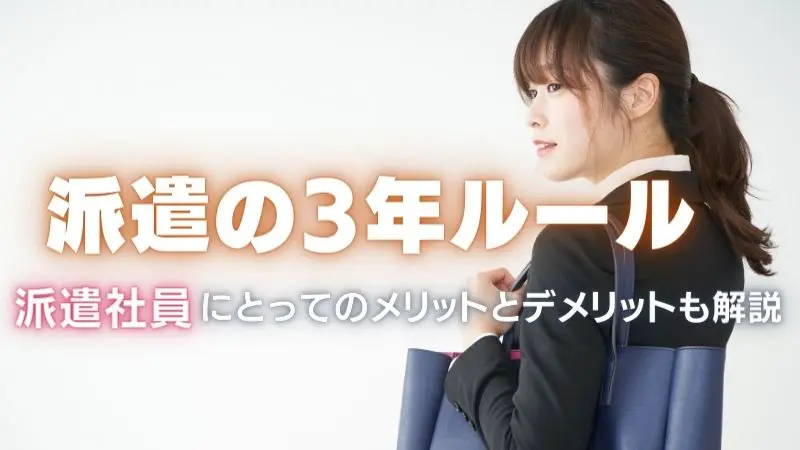
派遣の3年ルールとは?3年目以降の働き方や例外、メリット・デメリットも解説
目次
「派遣3年ルールという言葉は耳にしたことがあるけれど、詳しいことは知らない」
「派遣採用されてから3年が経ったけれど、この会社を辞めたくない。何か対処法はあるの?」
そもそも派遣3年ルールとは、同じ部署で有期雇用派遣社員として働ける期間が最大で3年間と定められているルールのこと。このルールは派遣社員であれば必ず理解しておきたい重要な規則です。
今回は、派遣3年ルールの概要やメリット・デメリット、派遣開始から3年が経過した後の対処法を紹介します。派遣3年ルールを知らない方や、派遣3年ルールの抜け道を知りたい方はぜひチェックしてくださいね!
※本記事エラベルが独自に制作しています。メーカー等から商品の提供や広告を受けることもありますが、コンテンツの内容やランキングの決定には一切関与していません。※本記事で紹介した商品を購入するとECサイトやメーカー等のアフィリエイト広告によって売上の一部がエラベルに還元されます。
派遣3年ルールとは?
派遣3年ルールとは、同じ部署で有期雇用派遣社員として働ける期間が最大で3年間と定められているルールのことを指します。
ちなみに有期雇用派遣とは、企業で派遣される期間があらかじめ決まっている雇用形態のことです。
派遣3年ルールの抵触日は、事業単位の抵触日が優先

抵触日とは、派遣社員が働き続けられる期間を超えた最初の日のことを指します。例えば抵触日が12月1日であれば、その前月の11月30日まで働けるということ。
しかしここで注意したいのが、事業所単位の抵触日と個人単位の抵触日は異なるということです。例えば派遣社員を1名、2020年4月1日から受け入れたとします。この派遣社員が実際に働き始めた日付が1年後の2021年4月1日だったとしても、事業所単位の抵触日は2023年の4月1日です。
個人単位で見れば抵触日は2024年4月1日ですが、事業単位の抵触日が優先されます。つまり個人単位の抵触日が来なくても、事業単位の抵触日が迫ることで派遣期間が終了することがあるので注意しましょう。
派遣3年ルールの抵触日を確認する方法

派遣の抵触日を知りたい場合は、派遣会社から発行される雇用契約書を確認しましょう。 組織単位の抵触日も雇用契約書に記載されています。
派遣3年ルールが例外になる5つのパターン
以下の5つの場合は、派遣3年ルールが例外になります。
- 派遣労働者が60歳を超えている場合
- 無期雇用の派遣労働者として働いている場合
- 産前産後休業や育児休業、介護休業を取得している社員の代わりに働く場合
- 終期が明確な有期のプロジェクト業務に派遣されている場合
- 日数限定で働いている場合
(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下である場合)
つまり、この5つのパターンに該当する場合は、派遣社員であっても同じ部署で3年以上働けるんです!
派遣3年ルールと5年ルールの違い
派遣三年ルールの他に、5年ルールという言葉が存在します。言葉は似ていますが、その内容は大きく異なります。
5年ルールとは同じ職場で5年以上働くことによって、無期雇用として契約してもらうことができる法律のことを指します。無期雇用社員として働きたい場合は、申し込みをする必要があります。自動的に無期雇用に切り替わるわけではない点に注意しましょう。
また無期雇用社員になれば、契約期間が無期限になるため雇用が安定します。しかし有期雇用に比べると責任が重くなったり、正社員へステップアップしづらくなったりといったデメリットも存在します。
それぞれのメリット・デメリットを確認して、自分は本当に無期雇用契約をすべきかどうか判断しましょう。
派遣3年ルールの2つのメリット

派遣社員は同じ部署で3年しか働けないと定められている派遣3年ルール。一見すれば派遣社員側のデメリットが大きそうな気もしますが、実はメリットも存在します!
1. 先が見えない状態から解放される

派遣3年ルールが採用されていない時代、派遣社員から正社員を目指す方は「いつまで派遣社員の期間が続くのだろう」と不安に思っていたことが多かった様子。
しかし、派遣3年ルールが採用されたことで、3年間働けば無期社員や契約社員といった別の雇用形態で働かせてもらえるかどうかの結論が出るようになりました。派遣3年ルールがあるおかげで「いずれは別の雇用形態になる」という先の見えない状態から解放されるようになったというわけです。
2. 無期社員になれる可能性が上がる

派遣3年ルールがあることで、無期社員になれる可能性が上がります。 上述したように有期雇用派遣社員は同じ部署で3年以上働くことができませんが、勤務先の企業から実力を認めてもらえば、3年働いた後に無期社員として採用してもらえる可能性が上がります。
会社側としても新入社員を入れて、1から教育するよりも派遣社員をそのまま受け入れたほうがコストがかからずに済みます。また、無期社員になれば、契約期限が無期限になり雇用が安定する点もメリットと言えるでしょう。
派遣3年ルールの2つのデメリット

派遣3年ルールのメリットを紹介しました。しかし、もちろん派遣3年ルールにはデメリットも存在します。
1. 3年を待たずして契約が解除される場合がある

派遣社員として契約している場合、3年以内に契約を解除されてしまう場合があります。 派遣社員に3年以降も続けて部署で働いてもらうために、企業側は有期雇用派遣以外の雇用契約に変更しなければなりません。
例えば有期雇用派遣から無期雇用派遣契約や正社員契約に変更した場合、企業側は業績不振などがあったとしても簡単に契約を解除できなくなります。有期雇用派遣社員を雇い続けたいと考えている企業ほど、3年以内に契約を解除する可能性が高い点は頭に入れておきましょう。
2. 3年経っても無期雇用の場合、直接雇用してもらえる可能性が低くなる

派遣期間の3年を終えて雇用形態を変更する際、直接雇用ではなく無期雇用になるとずっと派遣社員として働き続ける可能性が高くなります。
これは直接雇用を目指している方にとっては、デメリットに感じられる部分でしょう。
派遣3年ルールの抵触日を迎えた後の選択肢

派遣されてから3年が経った後、派遣社員にはどのような選択肢が残されているのでしょうか。
ここからは、以下4つの派遣社員が派遣3年ルールの抵触日を迎えた後のキャリアの進め方を紹介します。
1. 同じ派遣先の別の部署に異動する

派遣3年ルールは同じ部署で適用されます。つまり同じ派遣先であったとしても部署を異動すれば、また新たに3年間働くことが可能。
例えばその会社の事務課で派遣社員として2年間働いた後に、同じ会社の経理課に異動したとします。この場合は事務課で2年間はリセットされ、新たに経理課で3年間働けるようになるわけです。
2. 別の派遣先で働く

派遣会社に別の派遣先を紹介してもらい、異なる派遣先で働くことも一つの選択肢です。 前回の職場と同じような仕事を行う企業に派遣されることも有効ですが、キャリアアップのために別の業務を行う企業に移るのも賢い選択ですよ。
しかし、前回の職場と別の業務を行う企業を希望する場合、ある程度のスキルがないと採用されないことは頭に入れておきましょう。
3. 派遣会社の無期雇用社員になる

派遣会社より有期雇用から無期雇用に契約を変更してもらえば、派遣3年ルールの対象外になります。
派遣会社によって、無期転換制度があるかどうかや無期転換のための条件はさまざま。無期雇用に関する詳細を把握していない方は、派遣会社に問い合わせましょう。
4. 派遣先企業と直接雇用契約を結ぶ

派遣先の企業と直接雇用契約を結ぶことができれば、3年目以降も働き続けることができます。
しかし、派遣採用から直接雇用になることで勤務条件の自由度や収入が減ったり、仕事が辞めにくいと感じたりすることも…。たしかに直接雇用契約を結べば、継続して働けるというメリットがあるものの、その分デメリットがあることは理解しておきましょう。
ちなみに直接雇用契約を依頼してもらうために、派遣社員ができることは以下の通り。
- 自分の得意分野を活かせる企業で働く
- 報連相などの社会人としてのマナーを徹底し信用してもらう
- 社員とのコミュニケーションを大切にする
上記のポイントを心がけることで、企業から信頼され直接雇用契約を打診される可能性が高くなるでしょう。
まとめ
派遣3年ルールは派遣社員が必ず把握しておくべき重要な規則です。しかし上述したように派遣先企業と直接雇用を結んだり、部署を移動したりすれば3年目以降も働くことができます。
3年経っても同じ会社で働きたい場合は、今回紹介した方法の利用を検討してくださいね!

「選ぶをもっと楽しく」をコンセプトに、専門家・愛好家・体験者の方にご協力頂きながら、買い物やサービス選びに悩む方たちをサポートします。一人ひとりにフィットした情報に届け、皆さんの「したい」を叶えます。
※記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がエラベルに還元されることがあります。メーカー等の依頼による広告にはPRを表記します。
※掲載されている情報は、エラベルが独自にリサーチした時点の情報を掲載しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。